氷を調べていたときに知りましたが、日本は積雪量で世界一なんですね。年間降雪量世界ベスト3は日本の青森市、札幌市、富山市のようです。雨が多い原理と同じなのでしょうか。

そんな寒い中でも数多くの生物がいるのですね。好冷生物と呼ばれる-20~20℃で生きる生物。体温が低いほど活動しにくくなるのが通常の中で、寒い方が調子がいい生物がいるそうです。不思議ですね。

コオリミミズは適温が0℃という不思議な生物だそうです。昨日調べたATPの生産効率が非常に高いのですね。その生成速度はターボのようで、ATP濃度が他の生物より高いと。コオリミミズは氷を溶かす藻を食べて氷河の保持に貢献し、鳥に食べられる生態系の一部で、ときには食べられても消化管を通過して他の地域に分散していくようです。

ホッキョクジリスは体温が氷点下になっても生きているそうです。体温が氷点下になると血液が凍るはずですが、ホッキョクジリスの血液は凍らずに流れると。脳の凍結をも防ぐこともできるようで、マイナス50℃のツンドラ地域で生きていると。マイナス50℃で生物がいるのですね。生物の適応能力はスゴイですね。

氷下魚(コマイ)も氷点下の環境で血液が凍らない生物だそうです。血液中に凍結を防ぐ不凍物質を持っているのですね。キノコも凍結から身を守る不凍たんぱく質を持っているそうです。内部の氷に付着して大きくなるのを防ぐそうで、魚の5倍の不凍作用があるとか。


不凍能力を持つ生物が多いのは、血液が凍ってしまってはさすがの好冷生物も生存が難しいからなのですが、そんな中で、ナンキョクユスリカは血液が凍っても死なないそうです。このメカニズムはまだ解明されていないみたいです。血液が凍った状態でどうやって生きてるのでしょうね。
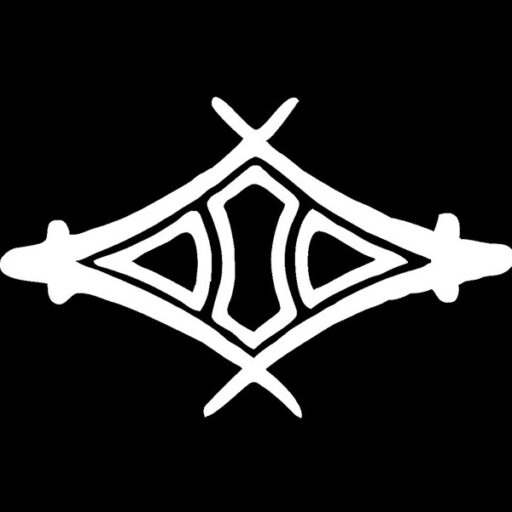
他にはもちろん、細菌、一部の地衣類、先日調べたアイスアルジーを含む氷雪藻、植物プランクトンも寒い中で生きていく能力を持っていると思われます。人は17℃くらいが限界だと言われていますが、水が凍るような環境が死の世界ではなく、たくさんの生き物がいる世界であるのも好冷生物の存在のおかげですね。好冷生物スゴイ。地球スゴイ。


