キーストーン種や団粒を調べていると、ビーバーやミミズは生態系エンジニアだという表現が良く出てきます。ビーバーは、樹木を切り倒してダムを作り、せき止められて出来た湖には、水鳥・カモノハシ・湿生植物が新たに生息するそうです。ミミズは、団粒を作り出して土壌を改良し、植物や微生物が生育する場所を提供しているのだとか。モノづくり、建設、土木工事のようなイメージからエンジニアと言われているのでしょうか。
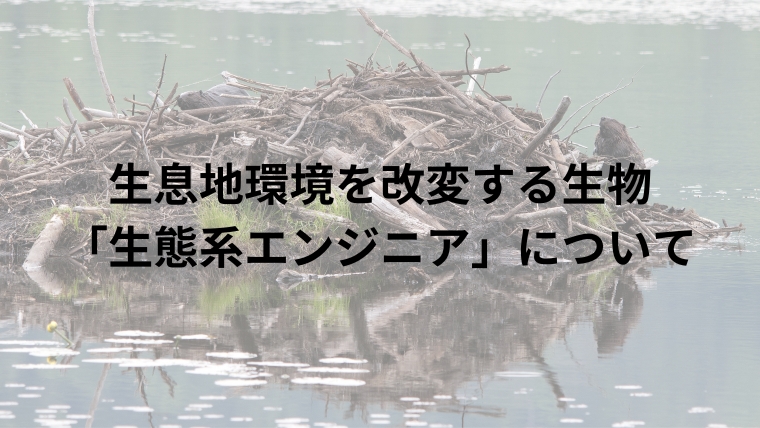
ゾウは森の庭師とも呼ばれ、木を倒したり、やぶを踏み分けてや動物の通り道を作ったりするみたいです。重機による道路工事のような感じでしょうか。また、ゾウの足跡がプールになってカエルが育ったり、水がないときの避難場所になったりするそうです。足跡だけでもかなりの大きさですよね。ゾウ、スゴイ。

また、キツツキやオオアルマジロは穴を掘るそうで、その穴が他の生物の住処となっているようです。穴あけ工事ですね。穴の中は、温度や湿度が一定のため、安定した住処になったり避難所になったりするそうです。キツツキは木を堀り、オオアルマジロは土を堀り、ウニは岩を掘るそうです。穿孔生物と呼ぶそうですが、ウニも生態系エンジニアなのですね。ウニの作る穴は、生物の数が外に比べて約3倍にもなるのだとか。ウニ、スゴイ。
他には、ハマキムシが葉っぱを巻いて葉巻を作ると、その丸まった葉のスペースに昆虫が隠れたり、温度変化を免れたりしているそうです。これはテント張り工事のような感じでしょうか。また、ホソウミニナという巻貝が集まると、地面が柔らかい干潟の上に硬い貝殻の基盤ができ、その上に多くの生物が生息しているのだとか。基礎工事や護岸工事のような感じですね。
生態系エンジニアは、かなりの数の種が該当するようです。自らの営みを行いつつ、環境を改変して、他の生物の役にも立つというはスゴイことですね。生態系エンジニア、スゴイ。地球の生態系、スゴイ。


