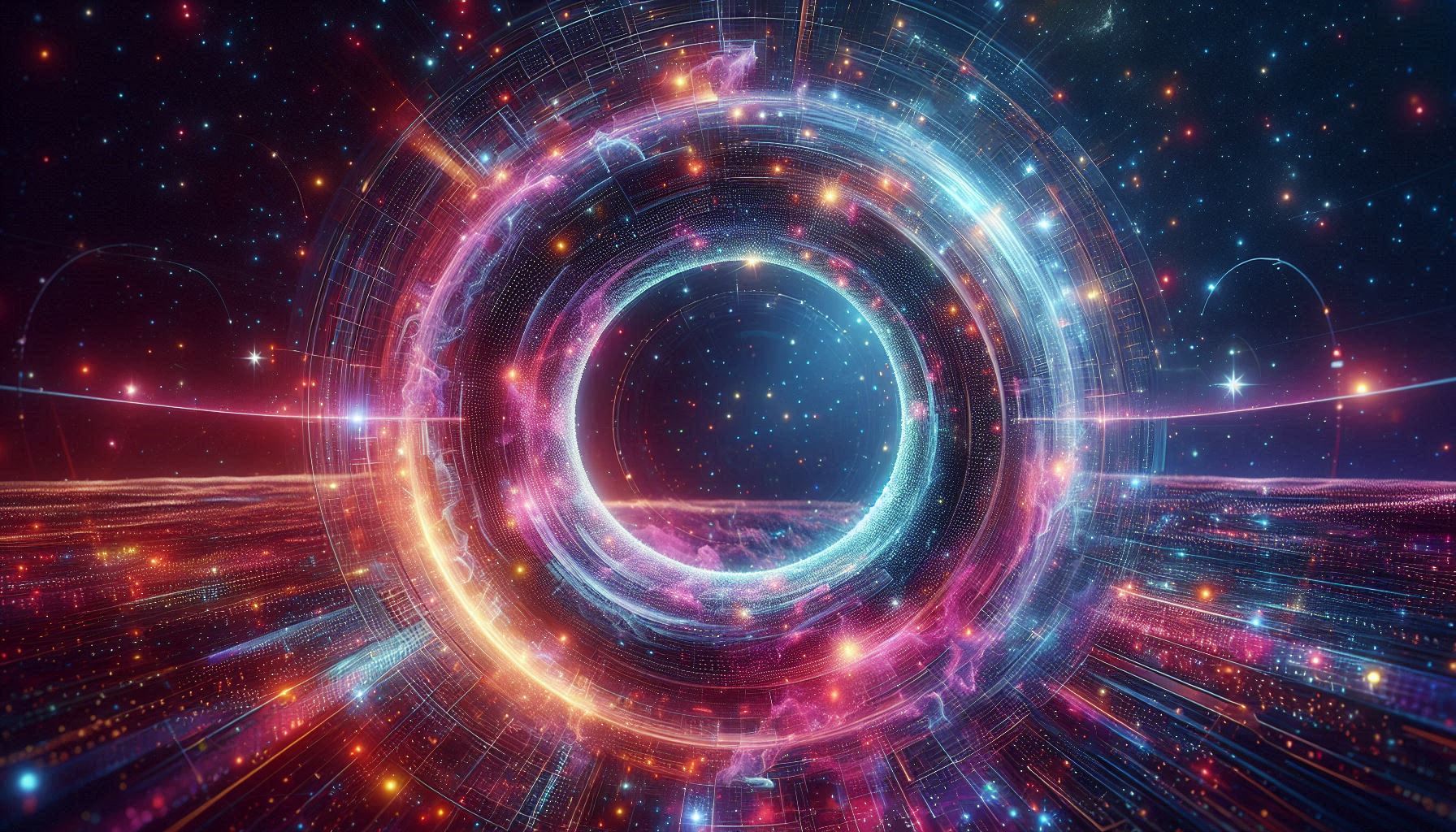ジオスペースを調べていると、バンアレン帯と呼ばれる放射線帯の形がトーラス状である、と出てきました。トーラスとは、円を回転させてできる環状の回転体のことのようで、ドーナツのような形をしているものが代表なようです。自然の中にはトーラス状になっているものも多くあるようで、ジオスペースの中にも、放射線帯、地磁気圏、プラズマ圏、酸素イオントーラスなどはドーナツ型に分布しているようです。磁石のように離れたN極・S極があり、互いに引き寄せ合うような力の動きはトーラス状になるのでしょうね。
魚の群れもトーラス状に泳ぐことがあるみたいですね。一定の範囲を旋回しながら泳ぐときに立体的な群れの状態で回転すると、ドーナツ状になるのでしょうね。水中を泳ぐ生物や、水などの流体にトーラスが現れるのかもしれません。流体が、一定の大きさの箱に閉じ込められるように動く場合、左右に旋回することができて、上下にも旋回することができるように、トーラス形状に動くのが最も自然な形なのでしょうね。
また、トーラス対流と呼ばれるトーラス状に対流する現象もあるようです。水の入った容器をろうそくの火で暖めると、温度が高くなった水が容器の中央を上に移動して、水面で冷やされて容器の端の方から下に移動すると、ドーナツ状に対流する動きになると思われます。閉じられた空間内で、中央部分が上方か下方かに動くと、トーラスの形状での対流が自然なのかもしれません。
他には果実もトーラス状になるものがあるみたいです。穴がないので、ドーナツ型ではないようですが、りんごやさくらんぼは上下が窪んでトーラス状になっているようです。枝についている側を梗窪(こうあ)、その反対側を萼窪(がくあ)と呼ぶそうです。梗窪は果実の重量を支えるために硬く、萼窪は花が咲いた後にがくが閉じるために硬くなるようで、それ以外の部分は内側から膨らんでいくため、上下の窪んだトーラス状になると思われます。みかんも、皮をむいた後の実の部分はトーラス状になっているように見えます。何らかの固定点2つと、自由に膨らむ部分が組み合わさると、トーラス状になるのかもしれません。

量子や分子の世界でもトーラス状になることがあるようで、原子核の周りの電子の存在確率を示すd軌道
の1つはドーナツ状のようです。また、DNAの複製を進行させるDNAクランプと呼ばれるたんぱく質もドーナツ状だそうです。ドーナツ状はトロイドとも呼ばれるのですね。

磁界、流体、果実、電子軌道、分子の世界でのトドーナツ型を調べてみました。マクロでもミクロでも現れる形状には何か意味がありそうですね。様々な現象に現れるトーラス、スゴイ。地球の神秘スゴイ。