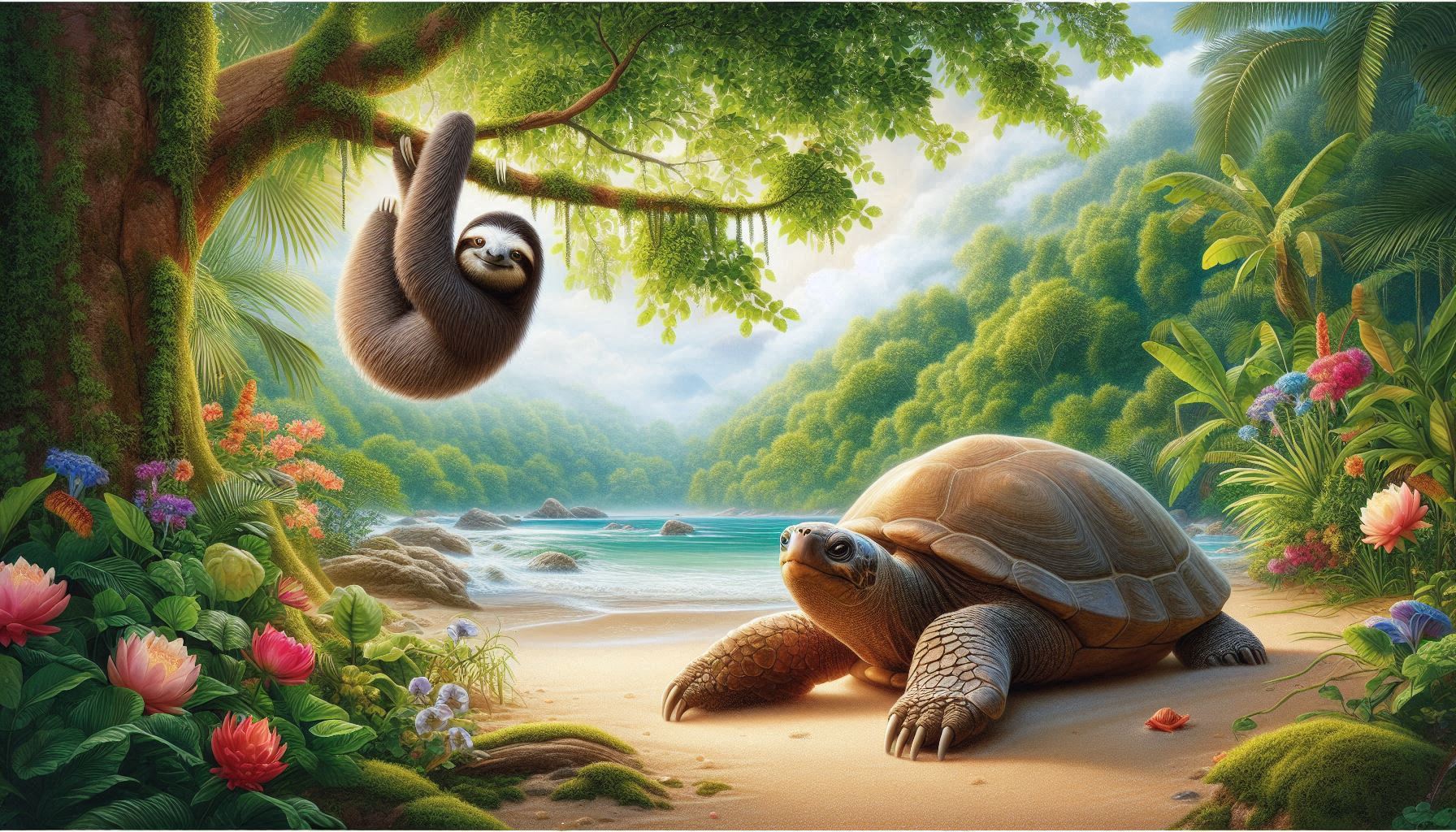電気を調べていると、生体内の電気の速度が出て来まして、思ったよりもゆっくりな速度だったのです。実測された脳の神経回路の電位の伝播速度は、0.2~1.5m/秒なのだそうです。生体のサイズにとっては一瞬で伝搬する速度だとは思われますが、電気の速度=ほぼ光速、というイメージと比べるとゆっくりに思えるのかもしれません。
そして、電気の速度も、ほぼ光速というのは電位の伝搬速度であって、電子の移動速度はかなりゆっくりで、カタツムリのような速度なのだそうです。銅などの導体中の電子の平均移動速度は0.075mm/秒という話もあるようで、実際は電線の周りに発生する電磁界が電力を運んでいるということのようです。電子の速度自体はもっと速いのですが、動きがランダムなので、移動距離を考えるとこのような速度になるのですね。調べてみましたが、カタツムリの移動速度は、1~2mm/秒のようです。
ゆっくり動く生物として有名な、ナマケモノの移動速度は40cm/秒、キーストーン種であるサバクゴファーガメの移動速度は8cm/秒だそうです。ゆっくり動く生物は、エネルギーの消費をギリギリまで抑えているそうで、ゆっくり動くのは身を隠すのにも都合がいいのだとか。他には、ゆったり生きる海の生物として、マナティー、ウミウシ、ニシオンデンザメも移動はかなりゆっくりだそうです。ニシオンデンザメは400年以上生きる長寿な生物でもあるようで、ゆっくり生きることと寿命も関係があるのでしょうか。

他には、大陸プレートの移動は18cm/年=0.000006mm/秒で、ゆっくりと動いているそうです。あまりにゆっくりなので実感することは難しいと思われますが、数千kmに及ぶプレートが常に動き続けているということは凄いことですね。

生体電気や電子の速度は意外でしたが、生命活動にとってはその生体電気の速度で充分であり、電力の伝搬にとってもその電子の速度で充分なのですね。速度自体にも、その速度であることの意味があると思われますし、ゆっくりな生物にとってもその速度がある種の生存戦略だと思われます。特にナマケモノは、戦わずにのんびりと平和で、自らに苔やガを住まわせて共生し、その苔を食べたり決まった場所に糞をすることで循環を作り出し、徹底した小食と低エネで生きているようです。ナマケモノ、スゴイ。

そして、地球の営みも、見えないところで壮大なスケールでゆっくりと動き続けているのですね。ゆっくり動くもの、スゴイ。速いものからゆっくりなものまで、地球に存在する速度のスケール、スゴイ。