海の生物を調べていると、海の生物は深いエリアと浅いエリアを行ったり来たりする鉛直運動を行っているという話が出て来ます。水圧の関係などもあり、動くのは水平方向ばかりのイメージがありましたが、垂直方向にも頻繁に移動しているのですね。その頻度は毎日になるようで、日周鉛直移動と呼ばれる壮大な日課なのだとか。
昼に潜り、夜に浮上する
海洋の生態系を支える、カイアシ類なのどの動物プランクトンは、食べられるのを避けるために、明るい日中には深海に潜り、暗くなると植物プランクトンを食べに表層に浮上するという、鉛直方向の上下移動を毎日行っているのだとか。小型の魚や甲殻類やオキアミなども同様の動きを毎日行っているようです。世界中の海で毎晩、たくさん海洋生物が浮上しているのですね。
壮大な移動
約100億トンにもなる何兆もの生物が繰り返す壮大な日課は、地球上で最大の動物の移動と呼ばれることもあるようです。浮上する生物の数があまりに多いため、船などのソナーでは、海底が上がってきたように見えるのだとか。夜に表層にいた大群は、朝日が海面を照らし始めると再び深海に潜っていくため、地球サイズで見ると日の出が東から西へ、太平洋→インド洋→大西洋と移っていくのに伴い、次々と大群が潜っていくように見えるかもしれません。そして、太陽が通り過ぎて日の入りが始まると次々に海面に向かって上昇する大群の動きは、まるで地球の自転に沿ったウェーブのようですね。

移動距離
ニホンウナギは水深約800~230mの間を移動するようで、水圧が3倍も変化する移動を毎日行っているのですね。新月では約230mまで浮上するウナギは、満月では明るくて他の生物に見つかる可能性が上がるため約300mまでしか浮上しないのだとか。ハダカイワシも約1000~300mを移動するようで、海洋生物の水圧適応は凄いですね。
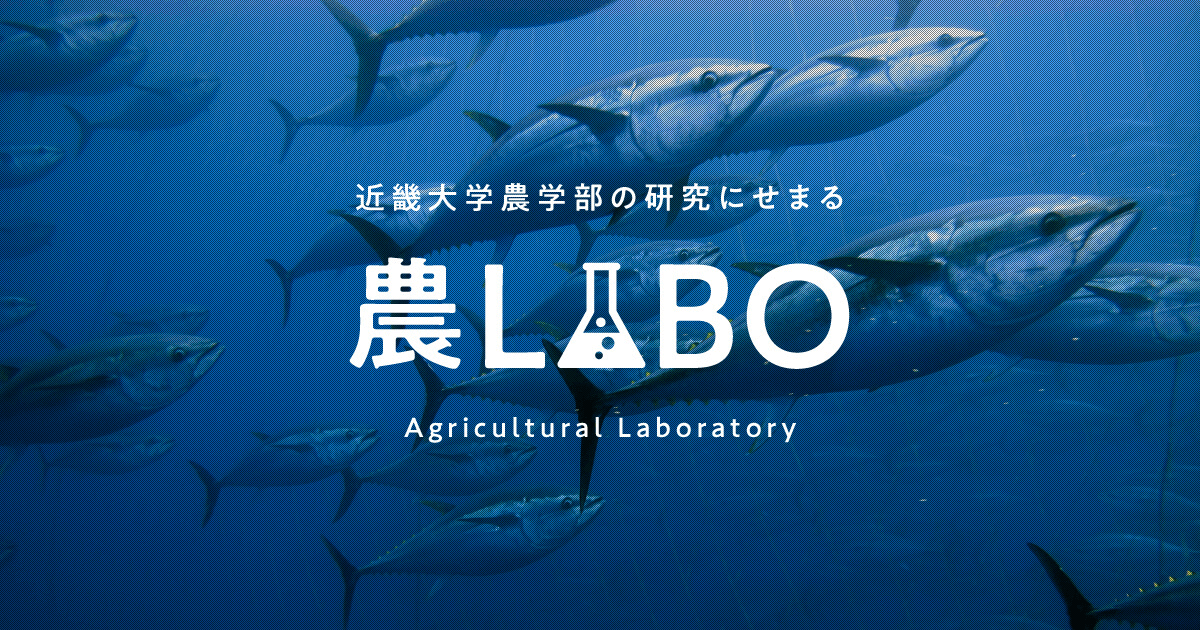
その他の日周鉛直移動
海洋に限らず、湖などの淡水の生物も日周鉛直移動をするようで、昼は湖の深いところに潜って隠れ、 夜は表層に上がって藻類を食べているのだとか。また、北極の海では、何週間も夜が続く極夜の時期で昼と夜の区別が付かない中でも、日周鉛直移動しているオキアミがいるようです。オキアミはわずかな光でも生物時計を合わせられる特殊な生物みたいですが、概日リズム=生命の営みなのですね。
日周鉛直移動スゴイ
少人数の人力でも流れるプールを作れることを考えると、日周鉛直移動も海をかき混ぜて循環を促しているのかもしれませんね。世界最大の壮大な日課となっているであれば、昼と夜と周期的にかき混ぜることにも意味があるのでしょうね。日周鉛直移動スゴイ。地球の壮大な営み、スゴイ。


