表面張力を調べていると土壌の保水の話が出てきまして、保水力の高い土壌の特徴として団粒構造という土の状態があるようです。団粒はだんご状になった大小の土の塊がバランス良く混ざり合っていて、適度な隙間がたくさんある状態だそうです。両立の難しい保水性と排水性をバランス良く備えて、通気性・保肥性に優れているため、植物が良く育つのだとか。
団粒のなかにも微細な通路があり、団粒と団粒の間には少し広い通路があるため、多すぎる水は重力に沿って下に流れ、表面張力によって留められる水は、団粒間に保水されるようです。水は一定の範囲で上下左右に細かく回流し、上層と下層に満遍なく水や栄養が行き渡るのだそうです。根が水を吸って水が減ると、この回流によって、すぐさま水が補給されるのだとか。団粒スゴイですね。
団粒をつくるためには、土と土をくっつける糊のようなものが必要で、根の腐敗物や土中の細菌や小動物が出す粘質物が糊の役割を果たしているという説があるそうです。この団粒をつくる生物の代表がミミズで、ミミズが生み出す糊は耐水性で丈夫なのだそうです。ミミズは、落ち葉などを分解して、多くの微生物を含む良質な団粒を生産する生態系エンジニアなんですね。
土壌にいる微生物も常に活発というわけでなく、有機物などの資源から離れると休眠状態になるそうです。ミミズは休眠状態の微生物ごと体内に取り込み、同時に取り込んだ有機物によって微生物を起こして分解を促すのだとか。ミミズ、スゴイ。落ち葉に含まれているポリフェノールは、他の生物にとっては毒になり食べることができないそうで、ミミズはこのポリフェノールに耐性があるようなのです。ミミズ、スゴイ。
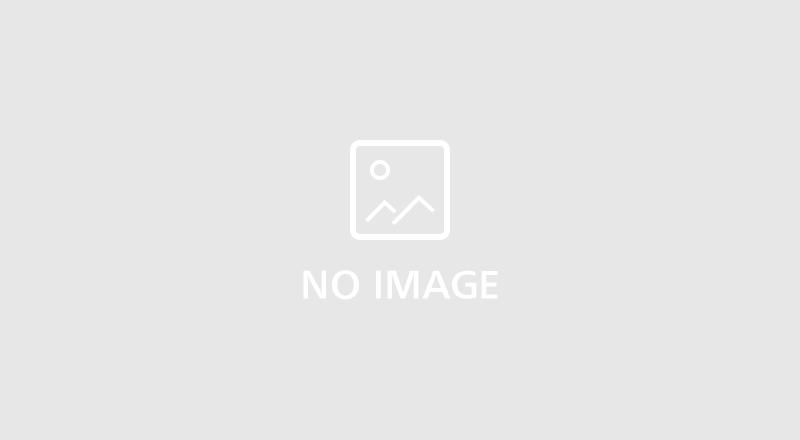
団粒を調べていたら、ミミズのスゴさになってしまいましたが、団粒は、隙間があるため植物も根を伸ばしやすく、隙間に多くの微生物が住まわせることができ、生態系を豊かにする土壌そのもののようです。団粒スゴイ。地球の生態系スゴイ。


