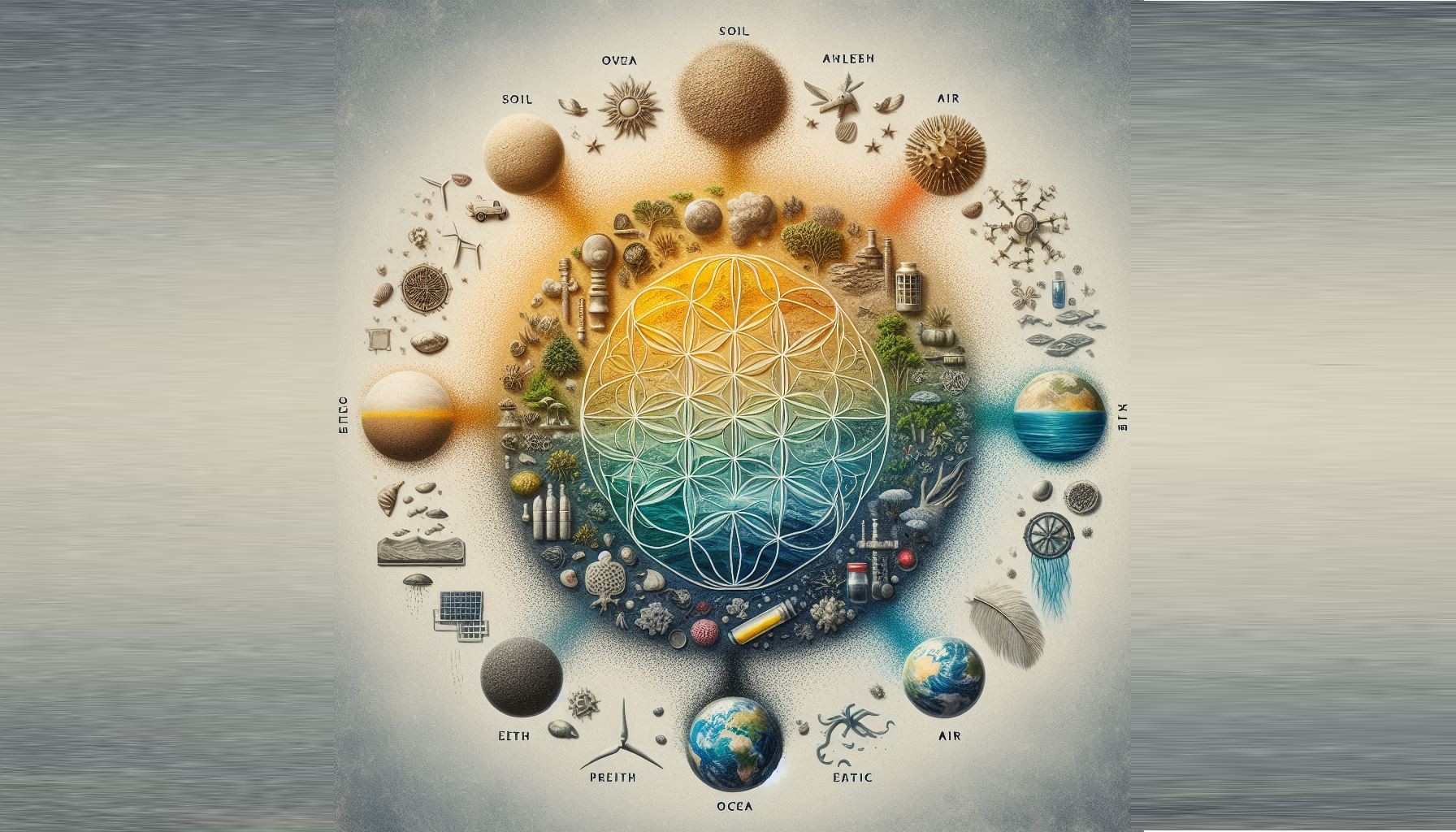コケ類や地衣類を調べていた時に、コケ類は重金属を、地衣類は放射性物質を蓄積して、土壌を浄化する働きがあるということが出てきました。他にも、多くの植物が苦手とする金属類が多く含まれる土壌に生育して、土壌にとってマイナスになる物質を蓄積する、ハイパー・アキュミレーターと呼ばれる植物がいるのだとか。
ウコギ科のコシアブラはマンガンを、オシダ科のヘビノネゴザはカドミウムや鉛を、アブラナ科のスタンレヤ・ピナータはセレンを、吸収・蓄積するそうです。どうやら、これらの植物は金属を蓄積することで虫から身を守っており、金属がない場合は虫が好まない物質を生成するのにエネルギーを使うため大きく育たないのだとか。金属を集めることには多角的に意味があるのですね。植物スゴイ。
土壌中の金属の次は、海洋上の石油を分解する石油分解菌と呼ばれる微生物についてです。石油分解菌は海にも陸にも広く分布しているようで、海水1ml 当たりの約10⁶個の細菌のうち、100~104個が石油分解菌だそうです。海水中に石油があると菌が増殖して全体の10%以上を占めるのだとか。特定の物質を栄養源として利用し、増殖できる性質のことを資化というそうですが、石油分解菌では特にアルカンを分解する菌が重要みたいです。石油分解菌が海洋の浄化をしてくれているのですね。
海洋上の石油の次は、大気中の二酸化炭素を大量に吸収する微生物についてです。チョンクスという愛称で呼ばれるシアノバクテリアで、今まで発見されたバクテリアの中でも大量の二酸化炭素を驚異的な速度で吸収する、優れた大気浄化能力を有しているのだとか。火山活動が活発な海底熱水噴出孔で発見されたそうです。多くの種を生む熱水噴出孔の生態系もスゴイですし、地球に必要な生物が存在しているということは本当にスゴイことですね。

プラスチックを分解する微生物を調べたときにも、様々な生物が土壌・水質・海洋・大気を浄化することで、生態系が守られたり、様々な物質が循環の輪に戻るのだと知りました。生物の営みがそのまま浄化に繋がっているという仕組み、スゴイですね。地球の浄化能力、スゴイ。